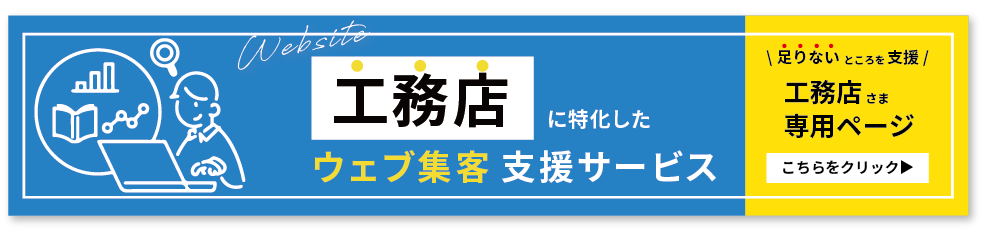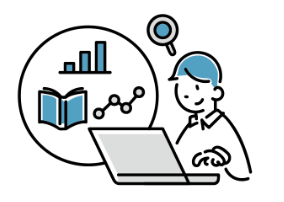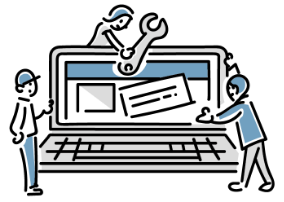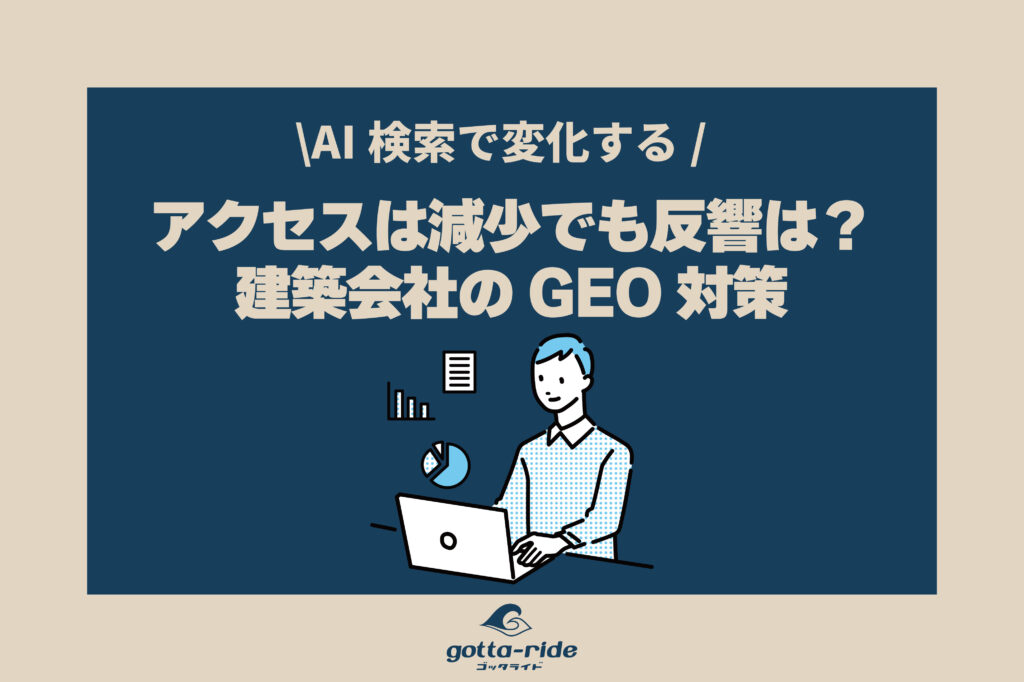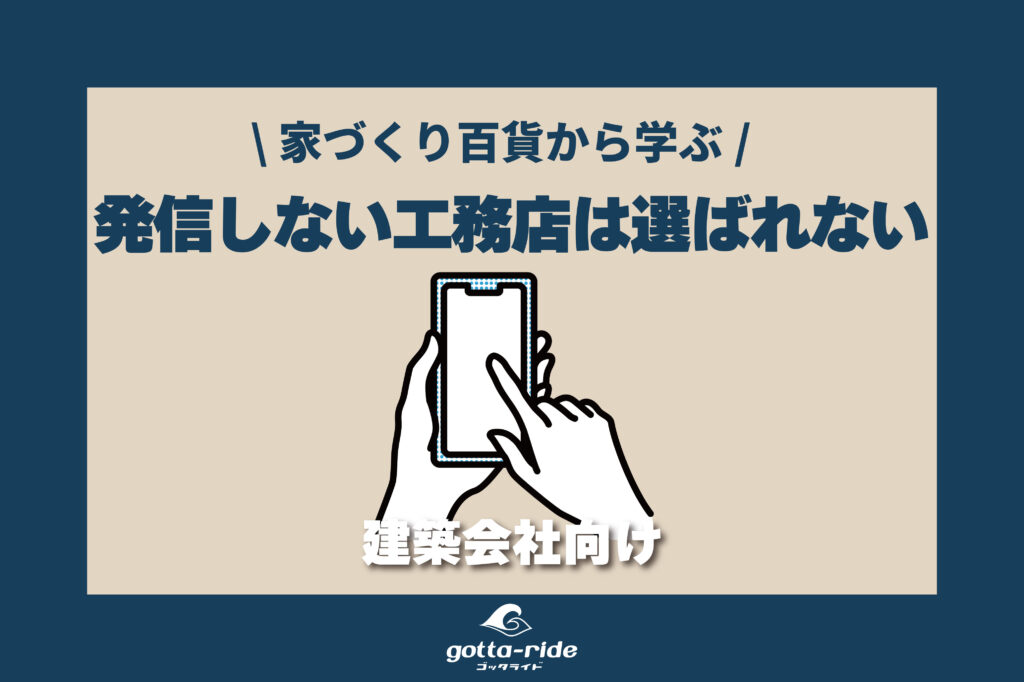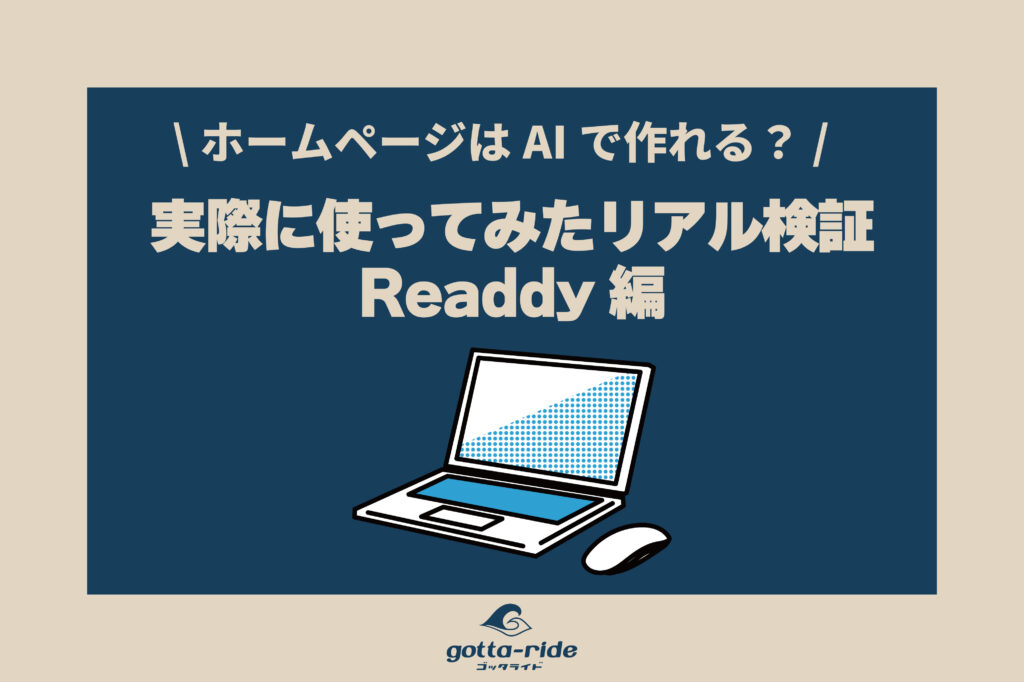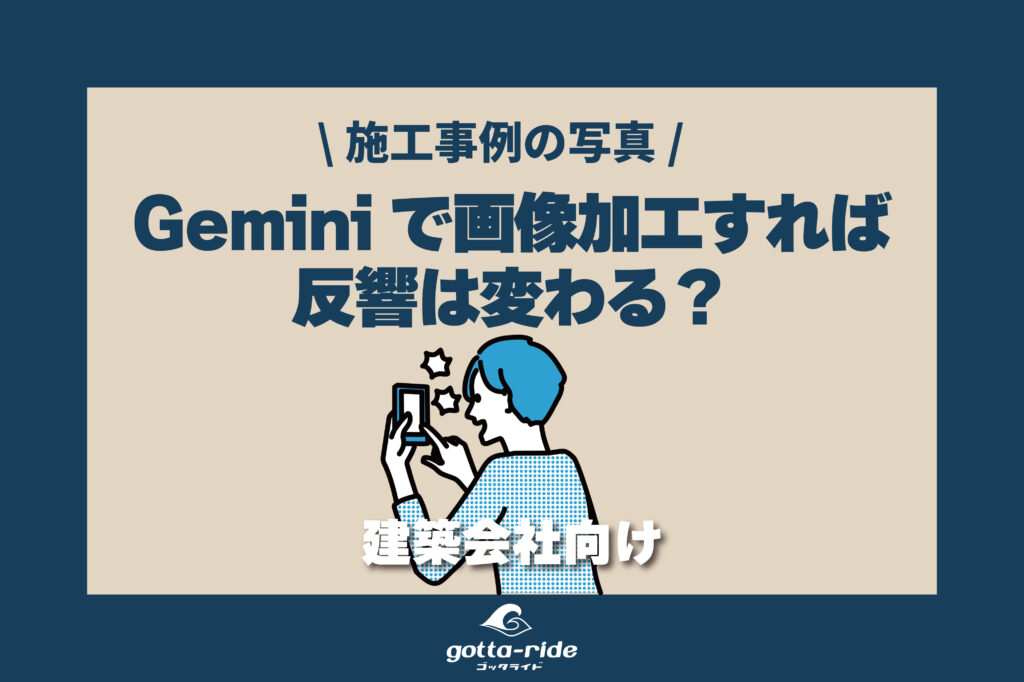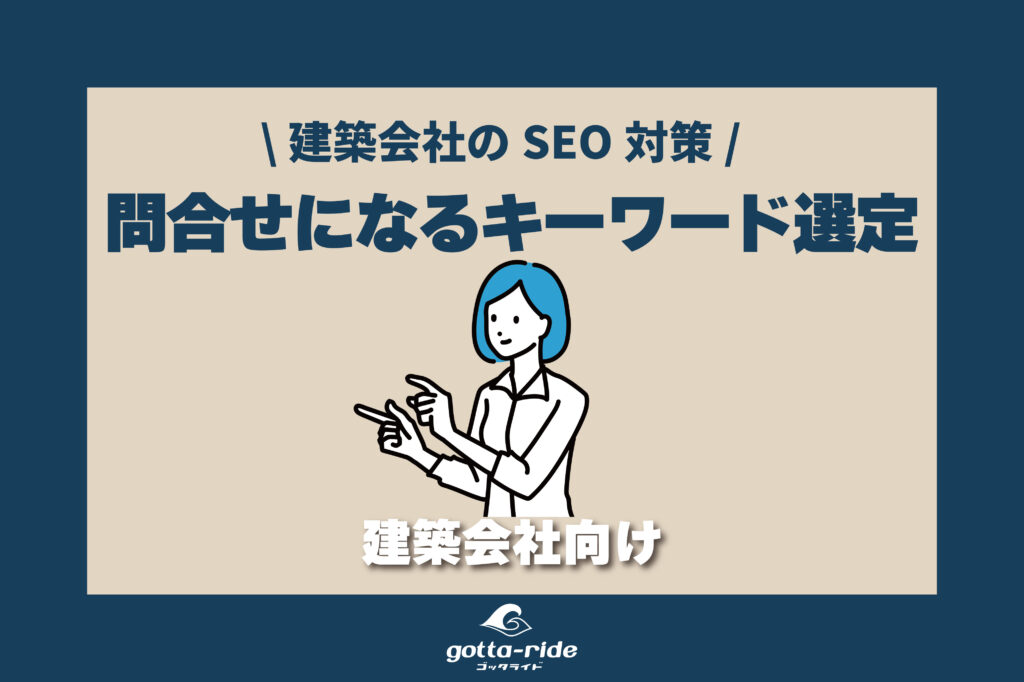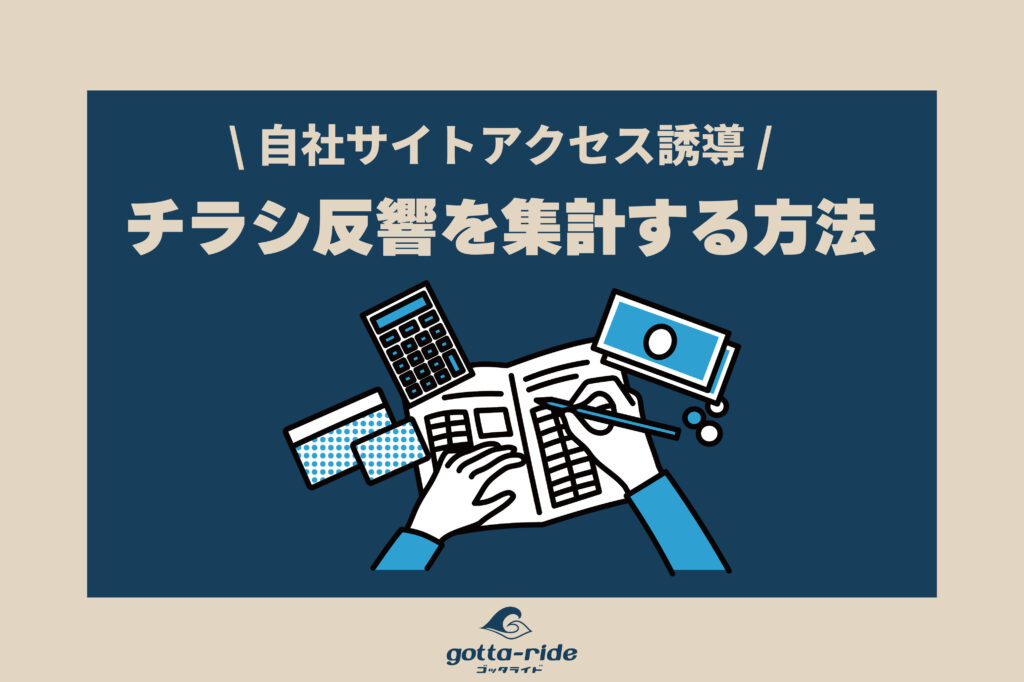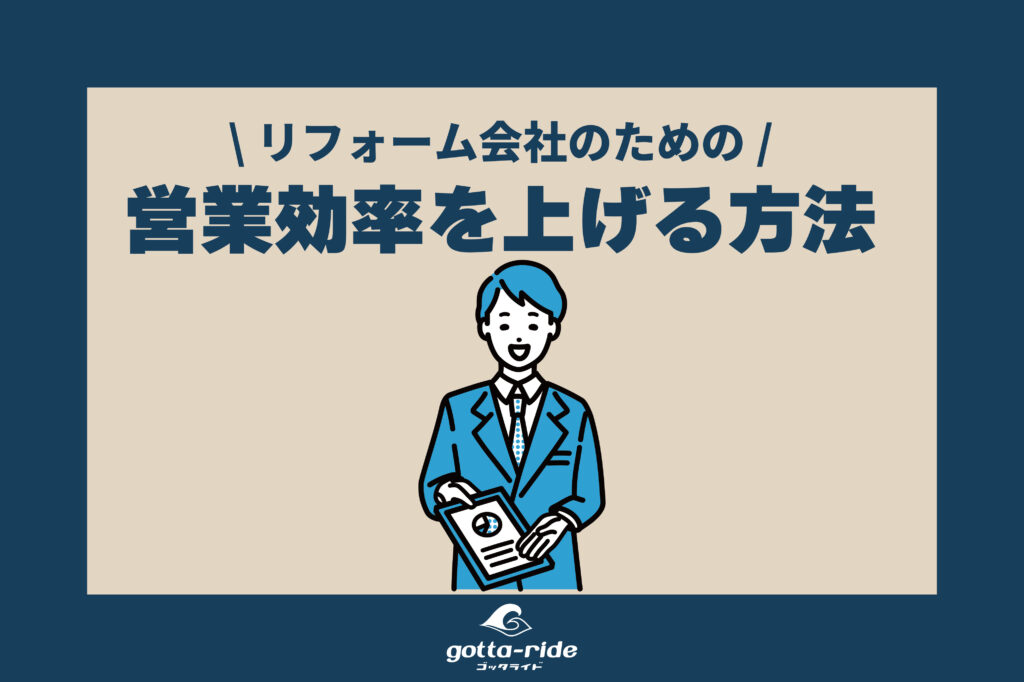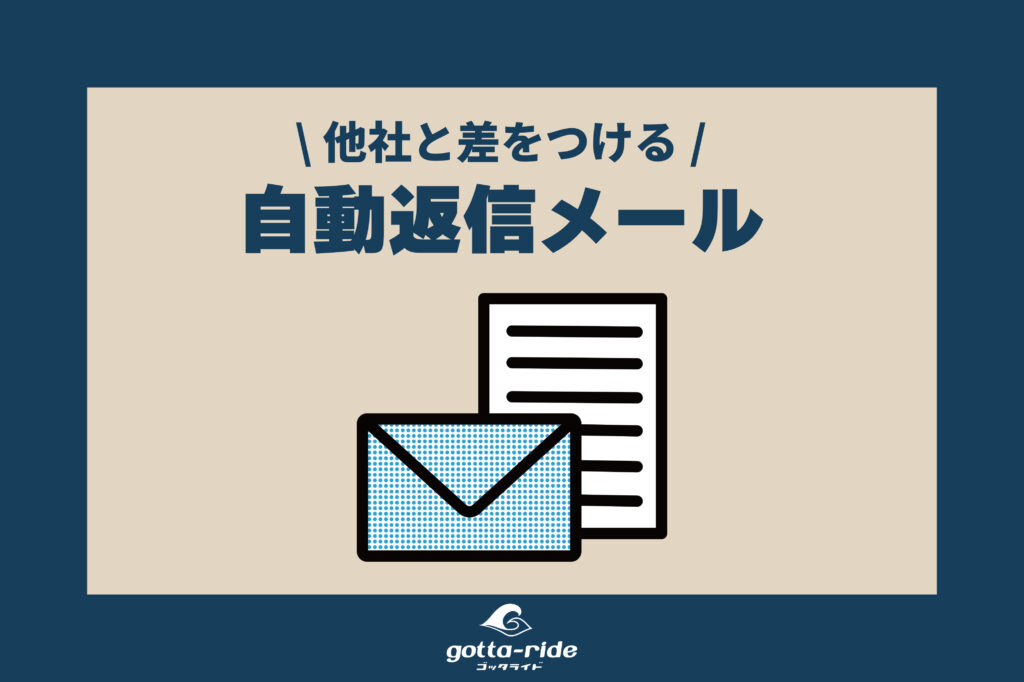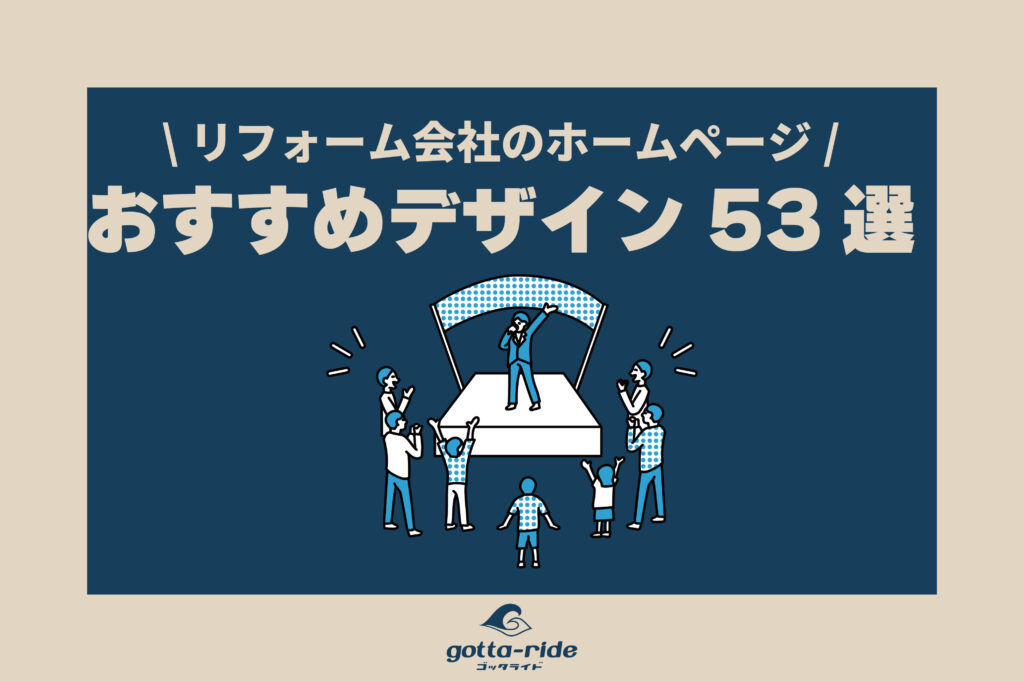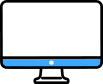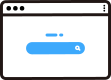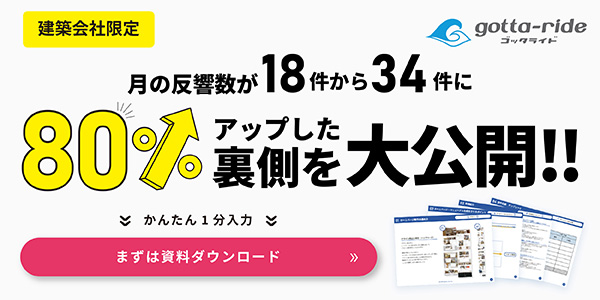ホームページ運用
工務店・リフォーム会社向け|営業生産性を高めるKPI管理と計画作成の具体例
公開日:2025/06/25
最終更新日:2025/06/25
こんにちは。工務店、リフォーム会社のホームページ集客支援のゴッタライドです。建築業界での営業活動において、「もっと反響を増やさなければ」「もっと広告費をかけないと売上が伸びない」と悩んでいませんか?
実は、工務店やリフォーム会社、塗装会社などの建築業界は、営業の仕組みを見直すだけで、反響数を増やさずとも売上を伸ばすことができるケースは少なくありません。とくに、営業のプロセスを数値で捉え、ボトルネックを見える化することで、無駄を省き、生産性の高い営業活動を実現できます。
「営業計画の立て方が分からない」「営業数値をどう管理すればよいのか迷っている」という方にとって、すぐに実践できる具体例と仕組みづくりのヒントが詰まった内容になっています。
この記事では、住宅業界・建築業界での豊富な支援経験をもとに、「営業の生産性を高める方法」について、計画の立て方・KPI(重要指標)の設計方法・業務の数値管理の実践例までをわかりやすく解説します。ウェブ集客やホームページ制作をするゴッタライドで、反響を伸ばすお手伝いをしていますが、営業での生産性を高める方法についても今回は言及していきますので、ぜひ、最後までご覧いただき、自社の営業改革の第一歩としてお役立てください。
建築会社の営業生産性向上の基本的な考え方
工務店やリフォーム会社、塗装会社などの建築会社が営業の成果を上げるには、「もっと集客する」ことばかりに目が向きがちですが、実は営業プロセスそのものを見直すことでも売上を伸ばすことが可能です。
とくに、住宅業界やリフォーム業界のように、お客様との商談が長期化しやすく、工数もかかる業種においては、営業活動を効率化する=生産性を高めることが極めて重要です。ここではまず、営業生産性を高める上での基本的なフレームワークとして、以下の5つのステップを紹介します。
- 理想(目標)を設定する
- 現状を把握する
- ギャップ(問題)を見つける
- 課題を明確にする
- 具体的な施策を実行する
この5ステップを順に整理することで、「今、何をすべきか」「どこに注力すればよいか」が自然と見えてきます。また、このプロセスの要となるのが【営業活動の数値化(KPI管理)】です。感覚ではなく数字で把握することで、判断の精度が上がり、チーム全体の動きも揃いやすくなります。
次の章では、営業活動を具体的にどう分解し、どのようにKPIとして設計していくかを「4つの営業ステップ」としてご紹介します。
リフォーム会社に特化したウェブ集客支援サービスのページはこちら
建築会社の営業ステップの4段階モデル
工務店やリフォーム会社、塗装会社などの建築会社の営業活動を「なんとなくの感覚」で進めていませんか?営業プロセスの全体像を明確にするためには、まずステップを分解し、それぞれに数値を設定することが大切です。ここでは、住宅会社・リフォーム会社に特に適した「4つの営業ステップ」を紹介します。
このステップに沿って活動を管理することで、どこに課題があるのかがはっきりし、生産性向上に直結する改善策が見つかります。
建築会社の営業ステップ①反響(コンタクトの獲得)
「反響」とは、お客様からの初回の接触・問い合わせ・資料請求・来場予約・お電話があった時点を指します。たとえば、以下のようなアクションがこれに該当します。
- 自社ホームページからの問い合わせ
- 資料請求の申し込み
- チラシや看板を見ての電話
- ポータルサイト(スーモ、ホームズなど)経由の反応
ここで重要なのは、「個人情報が取得できたかどうか」で判断することです。反響が発生した時点で、営業活動のスタート地点として1件カウントするのが基本です。
建築会社の営業ステップ②相談(初回面談・接客)
次に進むのは「相談(承談)」のステップです。これは、お客様と個別に対面またはオンラインで接触し、商談が始まった状態です。
たとえば、
- 来店・現場見学会などでの初回接客
- 電話での具体的なヒアリング
- オンライン面談や現地調査など
反響から相談へ進む率(=コンバージョン率)を上げることは、全体の営業生産性向上に大きく貢献します。
建築会社の営業ステップ③プラン・見積もり提出
次は、相談を経て、お客様に対して具体的な提案を行った段階です。
- 注文住宅なら「プランの初回提案」
- リフォームや塗装なら「見積もり提出」
このステップを【営業の「勝負所」】として扱う企業も多く、提出数・通過率を定点で確認することで、営業の提案力やクロージング力の向上につなげる指標になります。
建築会社の営業ステップ④受注(契約)
最後は「受注」=契約成立のステップです。契約書の押印日を基準に、明確にカウントできる成果指標となります。このステップまで到達した件数と、反響数やプラン提出数との比率を出すことで、
- ボトルネックはどこにあるのか?
- 見積もり提出後の受注率が低い理由は?
といった改善点の洗い出しがしやすくなります。
このように、営業プロセスを4つのステップで構造化し、それぞれを数値管理することで、どの地点で失注が起きているのか、どの段階で打ち手を打つべきかが明確になります。
次章では、この4ステップを「数字で捉える」ための具体的な集計方法とKPI設計のポイントを解説します。
建築会社のデータ整備とKPI設定の実践例
工務店やリフォーム会社、塗装会社などの建築会社が、「営業のどこに課題があるのか?」を正確に把握するには、感覚ではなくデータで営業活動を捉える仕組みづくりが欠かせません。この章では、前章で紹介した「4つの営業ステップ」をベースに、どのようにデータを整備し、KPIを設計していくかの実践例をご紹介します。
①建築会社の営業集計項目の基本設計
まずは営業プロセス全体を記録するための「集計表」を整備しましょう。以下はおすすめの項目例です。
|
項目 |
内容 |
|
顧客名 |
お客様の名前(匿名化でもOK) |
|
反響窓口 |
初回接点:HP、電話、チラシ、ポータルなど |
|
認知媒体 |
きっかけ:Google検索、SNS、紹介など |
|
顧客区分 |
新規 / OB / 管理顧客など |
|
CVポイント |
問い合わせ種別(資料請求、来店予約など) |
|
各ステップの日付 |
反響発生日 / 初回相談日 / プラン提出日 / 契約日 |
ここでのポイントは、「いつ・誰が・何から・どこまで進んだか」を一元管理することが重要です。
②建築会社の営業集計対象は「未受注も含める」こと
「受注した案件だけ記録している」という会社も多いですが、失注や途中離脱の情報にも大きな価値があります。すべての反響案件を、途中で止まったとしても入力しておくことで、
- 各ステップでの到達率(コンバージョン率)
- どのステップで脱落が多いか
- ボトルネックの発見と施策立案
といった分析が可能になります。
③建築会社の営業集計期間は「過去1年」がおすすめ
季節変動や繁忙期の影響を踏まえるためには、過去12ヶ月間のデータを整備するのが理想的です。とはいえ、件数が多く大変な場合は、まず「過去3ヶ月」に絞っても構いません。大切なのは、今の営業活動を可視化することです。
④建築会社の集客や営業の各ステップのKPIを数値化する
集計したデータをもとに、以下のように「ステップごとの通過率(コンバージョン率)」を算出してみましょう。
|
ステップ |
件数 |
前段階からの通過率 |
|
反響数 |
300件 |
— |
|
相談件数 |
150件 |
50% |
|
プラン提出 |
60件 |
40% |
|
受注 |
15件 |
25% |
このように数値化すると、「どのステップで失注が多いか」「改善すべき段階はどこか」が明確になります。
⑤建築会社の営業目標と現状の差を明確にする
たとえば、今年の受注目標を「20件」と定めたとしましょう。過去の通過率をもとに逆算すれば、
- プラン提出:80件(25%で20件受注)
- 相談件数:200件(40%で80件提出)
- 反響数:400件(50%で200件相談)
というように、目標達成に必要なアクション数が明確に可視化されます。
このようにして、「目標」「現状」「ギャップ(差)」を数値で捉えることで、営業チーム全体の動きが揃い、的確な対策を立てやすくなります。
次の章では、こうしたデータとKPIを月別の予算に落とし込み、毎月の営業活動を計画的に進める方法をご紹介します。
建築会社の実績からの目標逆算と月次予算の立て方
KPIを数値化し、過去の営業データを整備できたら、次にすべきは「目標の設定」と「月別の予算化」です。
ただし、目標は感覚で立てるものではなく、過去実績に基づいて“逆算”することがポイントです。ここでは、受注数・売上目標を実現するために、どのように具体的な数値へ落とし込んでいくのかをご紹介します。
建築会社の過去データを基にした逆算式の考え方
たとえば、過去1年間のデータが以下のようだったとします。
|
ステップ |
件数 |
通過率 |
|
反響数 |
360件 |
— |
|
相談数 |
180件 |
50% |
|
プラン提出 |
60件 |
33% |
|
受注数 |
15件 |
25% |
この場合、15件の受注を得るには、反響が360件必要だったということがわかります。
建築会社の来期の目標を設定してみる
ここから来期の目標を設定するとしましょう。
- 受注件数を15件 → 20件に増やしたい
- 客単価を2300万円 → 2400万円に上げたい
- ⇒ 年間売上目標は4.8億円に
この場合、過去の通過率をベースに逆算すると、
|
ステップ |
必要数 |
算出根拠 |
|
プラン提出 |
80件 |
20件 ÷ 25% |
|
相談数 |
200件 |
80件 ÷ 40%(仮) |
|
反響数 |
400件 |
200件 ÷ 50%(仮) |
つまり、目標達成には400件の反響が必要という結論になります。
建築会社の通過率改善による別ルートも検討する
ただし、必ずしも「反響数を増やす」だけが正解ではありません。たとえば、
- プラン提出→受注の通過率を25%→30%に改善できれば?
- 反響→相談の率を50%→60%に上げられれば?
など、どのフェーズの効率を改善するかでも、必要な反響数は変わってきます。これが営業生産性向上の要であり、“量ではなく質”で目標に近づく戦略を描けるようになります。
建築会社の月別の予算に落とし込む
年間目標が定まったら、次はそれを月別に分解して運用可能な形に落とし込みます。
|
ステップ |
年間目標 |
月別目標(例) |
|
反響数 |
400件 |
33件前後 |
|
相談数 |
200件 |
17件前後 |
|
プラン提出 |
80件 |
約7件 |
|
受注数 |
20件 |
約1.6件(≒月2件を目標に) |
※繁忙期・閑散期がある場合は、月別に傾斜をつけて設計してもOKです。
建築会社の実績とのギャップを追い続ける
月別目標を設定したら、毎月の営業会議で「実績との差」をチェックするのが重要です。ギャップが出たら、
- 反響が足りないのか
- 提案率が低いのか
- 決定率が下がっているのか
など、どこに課題があるかが自動的に浮かび上がってくる仕組みになります。
このように、数字を根拠にした計画は、社員メンバー全員の意識を合わせる「共通言語」となり、感覚に頼らない営業体制を実現します。
次章では、このKPI設計と目標に対して、さらに粒度を細かくして効果的に管理する方法(商品分類やエリア別管理など)について解説します。
リフォーム会社に特化したウェブ集客支援サービスのページはこちら
建築会社の営業データの粒度を上げる具体策
ここでは、商品分類・顧客区分・エリア別管理で“本当に見るべき数字”を絞り込むことについて解説していきます。
工務店やリフォーム会社、塗装会社などの建築会社が、目標と実績を数値で管理できるようになったら、次にやるべきは「粒度を細かくすること」です。全体平均だけを見ていても、実は「伸ばすべき領域」「ムダな努力」「取りこぼしの多いゾーン」が埋もれてしまうことがあります。ここでは、営業データをより戦略的に分析するための具体的な分類軸をご紹介します。
【商品分類】工事単価や工事タイプで分ける
住宅やリフォーム業界では、1件の単価が数万円〜数千万円と幅広く、「1件=1カウント」では実態を把握できません。そこで、次のような分類が有効です。
|
商品群 |
特徴 |
例 |
|
A軍 |
高単価・提案型工事 |
増改築・大型リノベーション |
|
B軍 |
中単価・標準工事 |
キッチン・浴室など |
|
C軍 |
低単価・軽作業 |
水栓交換・網戸張替え など |
各商品群ごとに、反響数〜受注数・単価・粗利率を集計することで、「どの商品群に力を入れるべきか」が判断できるようになります。
【顧客区分】新規と既存で分ける
「新規顧客」と「既存顧客(OB)」では、営業の手法も受注までのハードルも大きく異なります。 以下のような区分で分けて管理すると効果的です。
- 新規顧客:はじめて問い合わせをしてきた人
- 管理顧客:過去に反響・接点があったが未受注(メルマガ読者、イベント来場者など)
- OB顧客:すでに取引実績がある顧客
それぞれに対して、集客施策もフォローアップ方法も変えるべきです。
【エリア別・店舗別】管理の仕方
拠点が複数ある会社や、広域で集客している会社は、以下のような地域・店舗別の視点も重要です。
- 店舗ごとの受注率・平均単価を比較
- 地域別に見た反響〜受注の動き
- 競合が多いエリア vs 自社優位エリア
これにより、エリア別の強化施策(例:広告配信の最適化、現場見学会の集中配置)などが可能になります。
【実践ポイント】集計表に「区分列」を追加するだけ
複雑に見えるかもしれませんが、やることはシンプルです。すでに使っているExcelやスプレッドシートに、
- 「商品群(A/B/C)」列
- 「顧客区分(新規/OB)」列
- 「エリア名」「店舗名」列
などの補助列を追加していくだけです。あとは、ピボットテーブルやフィルター機能で分類集計すればOKです。
このようにデータを多角的に切り分けることで、以下のような意思決定ができるようになります。
- A群工事はラッキーパンチだった。目標はやや控えめに
- C群は利益が薄いがOB客で安定して取れるので現状維持
- B群を今年は重点的に伸ばしたいから広告を集中させる
- ○○地域の反響は多いのに受注に繋がっていない。見直すべきは提案?価格?人材配置?
次章では、このように分類された営業データを活用しながら、限られた販促費(広告費)をどこに投資すべきか?その評価方法を具体的に解説します。
建築会社の販促費(広告費)の評価と最適配分
次は、成果の出る施策とムダ施策を数字で見極めることについて解説します。
工務店やリフォーム会社、塗装会社などの建築会社が営業生産性を高める上で、「どこに広告費をかけるか」は非常に重要な経営判断です。しかし、実際には以下のような課題を抱える企業も多いのではないでしょうか?
- SNSやポータルに出稿しているけど、成果が見えない
- 看板やチラシにずっと予算をかけているが、効果を評価していない
- インスタ、YouTubeなど「やった方がいい」と思って始めたが、続けるべきか迷っている
これらを解決するカギは、感覚ではなく「数字で評価すること」にあります。
販促経路と「認知媒体」を分けて管理する
まず大切なのは、「反響がどこから来たのか」を以下の2軸で分けて管理することです。
- 反響窓口:問い合わせが入った場所(HP、電話、来店 など)
- 認知媒体:お客様が最初に会社を知ったきっかけ(Google、チラシ、紹介、SNS など)
たとえば、
- 「チラシを見て電話した」 → 反響窓口=電話/認知媒体=チラシ
- 「YouTubeを見て問い合わせフォームから資料請求」 → 反響窓口=HPフォーム/認知媒体=YouTube
こう分けておくことで、販促チャネルごとの効果が明確に可視化されます。
媒体別の成果を「ステップ単位」で数える
たとえば、以下のように各チャネルごとの反響→相談→プラン→受注の数を集計します。
|
認知媒体 |
反響数 |
相談数 |
プラン提出 |
受注数 |
|
Google広告 |
100件 |
50件 |
20件 |
5件 |
|
ポータルサイト |
80件 |
10件 |
3件 |
0件 |
|
チラシ |
60件 |
30件 |
10件 |
2件 |
|
紹介・口コミ |
15件 |
12件 |
8件 |
5件 |
これを見ると、「紹介・口コミ」は反響数こそ少ないが、非常に高い受注率を誇っていることがわかります。一方で、「ポータルサイト」は大量の反響があってもほとんど商談・受注に繋がっていないことも明らかです。
1件あたりの獲得コストで評価する
販促費の“費用対効果”を明確にするには、以下のような指標を算出します。
- 1反響あたりの費用(広告費 ÷ 反響数)
- 1受注あたりの費用(広告費 ÷ 受注数)
たとえば、
- Google広告:広告費20万円/反響100件/受注5件 →
1反響=2,000円 1受注=4万円 - ポータルサイト:広告費30万円/反響80件/受注0件 →
受注0=費用対効果なし
このように数値化することで、「伸ばすべき施策」と「やめるべき施策」が明確になります。
すべてをやる必要はない。「やるべき施策」に絞るべき
工務店やリフォーム会社、塗装会社などの建築会社の中小企業・小規模事業者では、人も時間もお金も限られています。だからこそ、成果が見込めない施策に手を出す余裕はありません。
- 「Instagramもやった方がいい」
- 「YouTubeも始めたい」
- 「チラシも欠かせない」
こういった施策を“全部中途半端”にやるよりも、実績に基づいて効果が出ている施策に集中投資する方が、営業生産性は確実に上がります。
イベント単位でも評価ができる
たとえば「完成見学会」や「相談会」などの個別イベントごとに、
- 集客数
- 反響数
- 来場者からの受注数
- 投下した費用
を集計しておくことで、「どのイベントが費用対効果が高いか」を評価できます。年間の広告・イベント予算配分にも活かすことができます。
このように、販促活動は“感覚”ではなく“数字”で評価し、配分を最適化することが生産性向上の大きなポイントになります。
次章では、こうして整えた数字とKPIを営業会議やチーム内でどのように活用し、実行と改善を繰り返していくかを解説します。
建築会社の営業会議の質を高めるデータ活用とPDCA運用
次は、報告会から「意思決定の場」へ進化させることについて解説します。
工務店やリフォーム会社、塗装会社などの建築会社では、どんなに精度の高い営業KPIや販促評価ができても、それを現場で活かしきれなければ意味がありません。そこで重要になるのが「営業会議」のあり方です。
この章では、営業会議を単なる報告の場で終わらせず、改善アクションを生み出す場にするための仕組みと運用ポイントを解説します。
建築会社の営業会議でよくある課題
中小企業でありがちな営業会議の課題には、次のようなものがあります。
- 会議が「報告」で終わり、アクションが決まらない
- 「あの案件どうなった?」の確認に時間を消費してしまう
- データがバラバラで、議論の土台が揃っていない
- 計画を立てても振り返らず、行き当たりばったりになる
これでは、数字を使った経営判断や営業改善が進まず、ただの“情報共有会”になってしまいます。
建築会社の会議の目的は「次に何をするか」を決めること
理想の営業会議とは、「現状を確認した上で、次にどう動くかを決定する場」です。そのためには以下の要素が必要です。
- 現状の数字が会議前に共有されている(見える化)
- 課題(ギャップ)とその要因が明確になっている
- 担当者ごとに「次のアクション」が決まる
「○○のお客様は今どうなってますか?」ではなく、「○○のお客様には次に何をしますか?」を問いかけるのが営業会議のあるべき姿です。
建築会社のデータ連携 マーケティングと営業の橋渡し
もう一つ見落とされがちな重要ポイントは、マーケティングと営業の分断です。
- どの媒体から来た反響が売上に繋がったのか
- ポータルとチラシ、どちらの方が受注率が高いのか
- SNSの運用が実際に成約に貢献しているのか
これらを把握するには、マーケと営業のデータが連結されていなければ意味がありません。マーケティング施策の評価には、営業の最終成果(受注)が必要です。営業も、どこから来た顧客なのかを意識することで、対応が戦略的になります。
建築会社の計画はズレて当然だが「なぜズレたか」が重要
工務店やリフォーム会社、塗装会社などの建築会社の営業会議では、計画どおりに進んでいないことを「悪いこと」として扱うのではなく、「ズレの原因を探る」ための機会にしましょう。
- 想定より反響が少なかった → 広告訴求が弱かった?時期が悪かった?
- プラン提出からの受注率が低い → 提案スピード?競合に負けた?予算感?
- 承談につながらない → 初期対応が遅い?資料だけ送って放置?
こうした検証ができていれば、たとえ「計画未達」でも、次の改善策を実行できます。
建築会社のPDCAを「営業現場に回す」ための工夫
営業がそれぞれPDCAをしっかり回すためのポイントは以下のとおりです。
|
フェーズ |
具体的なアクション |
|
Plan(計画) |
数値に基づく目標設定(年間・月間・商品別) |
|
Do(実行) |
各担当者がアクションに落とし込んで動く |
|
Check(確認) |
会議でギャップ分析。なぜズレたか?を確認 |
|
Act(改善) |
来月のアクション・ルール・施策を修正 |
また、データがすぐに見られる状態(見える化)にすることも重要です。会議中にいちいちExcelを開いて確認するのではなく、共有フォルダやGoogleスプレッドシートなどで、関係者全員がリアルタイムでアクセスできるようにしておきましょう。
建築会社の塩漬け案件をどう管理するか?
営業マンが多忙で後回しにされがちなのが「すぐには決まらない案件」。いわゆる塩漬け案件です。ここにも明確なルールを設けましょう。
- ○日以上アクションがなかった案件は、フォロー部隊へ移行
- 営業からマーケ部門に引き渡し、メルマガ・LINEで再ナーチャリング
- フォロー結果によって、再び営業へ戻す or 顧客区分を変更
すべての案件に“次の動き”が設定される体制をつくることが、営業会議の質を高める最大のポイントです。
次章では、営業プロセス全体の中でも特に重要な、「取りこぼし防止」と「改善施策の検証」方法について、より具体的に解説します。
リフォーム会社に特化したウェブ集客支援サービスのページはこちら
建築会社の取りこぼしを減らす営業施策と改善サイクルの回し方
ここでは、ステップ間の“離脱”を防ぎ、受注率を高める仕組みについて解説します。
工務店やリフォーム会社、塗装会社などの建築会社が営業生産性を高めるには、「数字の管理」だけでなく、“取りこぼしを減らす”ための具体的な仕組み作りが不可欠です。どんなに反響が多くても、途中で離脱してしまうお客様が多ければ、営業の成果にはつながりません。
この章では、建築会社が営業プロセスの各ステップで起こりうる「離脱」を減らすための打ち手と、PDCAの実践方法を紹介します。
建築会社の取りこぼしを減らす営業施策①各ステップでの離脱理由を特定する
建築会社の営業のプロセスを4ステップ(反響→相談→プラン提出→受注)で見た場合、どこでどれだけのお客様が離脱しているかを数値で把握することが第一歩です。たとえば、
- 反響 → 相談 に進まない
┗ メールの返信が遅い、電話フォローがない - 相談 → プラン提出に進まない
┗ 提案までの期間が長い、信頼構築が不十分 - プラン提出 → 受注にならない
┗ 競合に負けた、価格が合わなかった、放置された
このように、「どこで止まったか」がわかれば、対策が打てるようになります。
建築会社の取りこぼしを減らす営業施策②見込み顧客の再活性化 フォロー体制を整える
一度接点を持ったお客様(いわゆる管理客・見込み客)に対して、再度関係を築く仕組みが必要です。以下のような手法が効果的です。
- メルマガの定期配信:見込み顧客に継続的に接触し、再CVを狙う
- LINE活用:イベント情報・施工事例などを配信し、再来店を促す
- 季節ごとのフォローキャンペーン:補助金、外壁点検、エアコン清掃など
こうした細かなフォロー体制が“再相談”や“再見積もり”に繋がる導線になります。
建築会社の取りこぼしを減らす営業施策③塩漬け案件の明確な「引き継ぎルール」をつくる
建築会社の営業担当者がすぐに対応できない案件は、「放置する」のではなく、会社全体で回収する仕組みが必要です。
例えば、
- プラン提出後●日以内にフォローがなければ、マーケ部門が追客
- 商談日から●週間以上反応がなければ、次回の営業会議で対応検討
- 「負けた理由」を記録 → 類似案件に活かす
ホットではないお客様(今すぐ客ではない)にも“次のステージ”を用意する体制が生産性を下支えします。
建築会社の取りこぼしを減らす営業施策④負けた案件を“資産”として残す
競合に負けた、価格が合わなかった、決め手を欠いた…。こうした「敗因分析」も、勝率を上げる貴重なヒントになります。他決した場合には、次の内容を記録しておきましょう。
- 契約に至らなかった理由のヒアリング・記録
- 提案資料の比較/営業トークの見直し
- 同業他社の強み・弱みを社内で共有
負けた理由を次に活かすことで、次回以降の勝率が上がる「仕組み化された学び」になります。
建築会社の取りこぼしを減らす営業施策⑤改善サイクルを数字で回す
実施した施策が本当に効果があったのか?を検証するには、以下の流れが有効です。
- 目標を設定する(例:相談化率33%→40%へ)
- 施策を実行する(例:反響後24時間以内に電話)
- 結果を計測する(例:施策実施前後の比較)
- 見直す/継続する(効果があれば標準化)
この繰り返しこそが、営業改善の本質です。数字を起点にしたPDCAを根気よく回し続けることが、やがて“勝ちパターン”の確立に繋がります。
このように、営業プロセスの中で「取りこぼしを防ぐ仕組み」を整えることは、反響数や広告費を増やすよりも費用対効果の高い改善手法です。
次の最終章では、ここまでの流れを踏まえて、営業生産性向上のための全体まとめと実践アクションの提案を行います。
建築会社の営業生産性を高めるために今すぐ始めるべきこと
ここまで、営業生産性を高めるための考え方から、KPI設計、目標の逆算、販促評価、会議運用、そして取りこぼし防止まで、一連の改善プロセスを具体的に見てきました。営業の成果は「勘と経験」に頼る時代から、数値に基づいた戦略と改善の時代へとシフトしています。
そのために、今すぐ始められるアクションを以下にまとめます。
建築会社が今すぐ取り組める5つのアクション
- 営業プロセスを4つのステップに分けて整理する
→ 反響 / 相談 / プラン提出 / 受注 で分類する - 過去1年分の営業データを集計して現状を見える化する
→ 未受注も含めた一覧表をつくり、ステップごとの通過率を把握 - 売上目標から逆算して必要な反響・相談数を算出する
→ 客単価・受注率をもとに計画数字を設計 - 販促媒体ごとの反響・受注率を数値で比較する
→ やるべき施策とやめるべき施策が明確に見えてくる - 月別・担当別・商品群別に目標を落とし込み、会議で定点観測する
→ ギャップを分析し、アクションを設定 → 改善へつなげる
成果を出すためのマインドセット
- 「数字が苦手」でも、感覚に頼らない判断を始めよう
- 完璧な計画より“まずやってみる”が大切
- 1年単位で改善を回せば、営業体制は確実に進化する
- 放置されている見込み客こそ、伸びしろの宝庫
最後に 改善は一歩ずつでOK
最初からすべてを整える必要はありません。まずは1つの指標、1つの表、1つの会議からでも始めることが、営業改革の第一歩になります。また、もし「自社の場合はどうしたらいいか?」というご相談があれば、ぜひ専門家に相談するのも一つの手です。一度仕組みを整えれば、後は少しずつ“回る営業体制”が構築されていきます。
ゴッタライドでは、ウェブ集客やホームページ制作・修正以外にも、このような営業生産性向上についてのアドバイスやコンサルティングなども行っております。数多くの建築会社の営業体制を見てきた経験を活かし、各会社にそれぞれ適した体制や集計方法などをご提案できますので、気になる方はお気軽にご相談ください。


 無料相談
無料相談 資料ダウンロード
資料ダウンロード お問い合わせ
お問い合わせ